いつも日本人とともにあった漆文化の伝統が風前の灯火に

日本人と漆の関係は縄文時代にさかのぼる。北海道函館市にある垣ノ島遺跡では、約9000年前の漆塗りの装飾品が出土した。中尊寺金色堂や金閣寺、日光東照宮など、日本の歴史の象徴となった建築物のすべてに漆が使われている。漆は日本人の生活・文化に欠かせないものとしていつもそばにあった。
ところが、ここ数十年の間に手軽なプラスチック製品や化学塗料などが増えて、漆の需要が減少。かつて岩手県の職員として漆産業の振興を担当していた浄法寺漆産業の松沢代表は、在職中から漆文化の将来に危機感を抱いていたという。
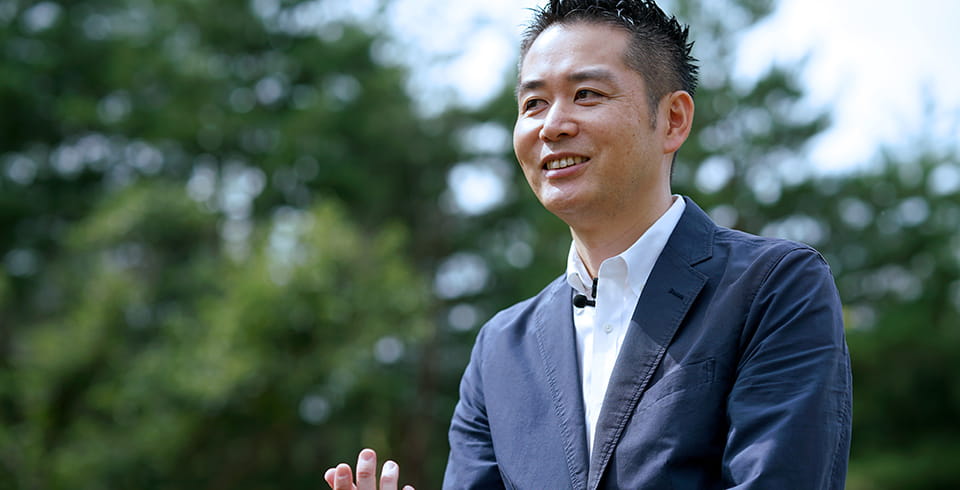
「漆は日本文化そのものであり、将来に受け継いでいくべきもの。漆には抗菌作用があるし、酸にもアルカリにも強いという性質もある。こんな素材は自然界でも珍しいです。在職中に漆に関わるさまざまな方と出会い、漆文化の伝承を職人さんたちにまかせっきりにしていてはいけないと感じました。それで、漆の魅力を広く啓発していくために、浄法寺漆産業を立ち上げたのです」
松沢さんが県職員を辞めることに対して「安定した職を手放すのはもったいない」と周囲の人は反対した。
「漆が身近な岩手県の中にいると、その大切さを実感しにくいものです。独立に際して私の背中を押してくれたのは、全国各地にいる職人さんたちでした。蒔絵の人間国宝・室瀬和美先生に相談に行くと「ぜひやってくれ」と言われ、その一言を力に踏み出すことができたのです」

岩手県は国内生産の7割を占める日本一の漆の供給地である。なかでも二戸市浄法寺の地域は最大の生産量を誇る。しかしながら、国産漆の生産量は30年前と比較して4分の1程度まで減少し、需要の約97%を中国などの外国産に頼っているのが現状だ。外国産は国産と漆の採り方が異なったり、成分に違いがあったりして、文化財を修復したところが傷みやすいなどのトラブルもあるという。
文化庁は国産漆を保護し、安定的な供給体制を構築することを目的として、平成30年度から国宝・重要文化財建造物の保存修理における漆の使用方針について、原則として国産漆を使うことを決めた。保存修理で必要な漆の量は年間約2.2トン。それに対し、国産漆は1.3~1.4トンしか生産されていないのが現状だ。この状況を打開するために、松沢さんは新しい漆採取の方法を模索した。
「漆の木を増やすにしても育つまでに時間がかかるし、漆掻きができる職人は高齢化が進み、後継者も育っていません。どうしようかと考えていたとき、衝撃波を植物に当てて、細胞を破壊し、液体だけを取り出す衝撃波破砕技術の存在を知ったのです」
衝撃波破砕技術を応用し、貴重な漆を無駄なく抽出する
衝撃波破砕技術は、高電圧の電気放電によって、音速を超える速さの衝撃波を発生させ、高い圧力によって細胞を壊す技術のこと。例えば、りんごに衝撃波を当てると、内部の細胞が壊されて、細胞と果汁が分離する。そのため、皮の上からストローを刺すと、ジュースのように飲めるのだ。技術研究の第一人者、国立沖縄工業高等専門学校の伊東繁名誉教授が中心となり、衝撃波破砕技術を漆に応用するための研究を行っているところだ。

「松沢さんから日本の漆の現状を聞いて、私も何かできないかと思いました。それで、漆をとる新しい方法を検討し始めたのです」
従来の漆掻きでは、6月から10月にかけて、職人が木に傷をつけて、丁寧に漆を集めていく。ウルシオールという成分濃度が高い漆がとれるものの、集まる量は少ない。漆の木は、植栽してから漆を採取できるようになるまでに約15年かかる。しかも、1本の漆の木から採れる漆の量は約200g。お椀が10個つくれる程度の量だ。
一方で、衝撃波破砕技術を使って漆を採取する場合、木や枝などの細胞を壊し、細胞と漆を分離させることができる。実証研究の結果、1本の漆の木から、漆掻きで採取したときの倍以上の漆を集めることができた。松沢さんはこれから漆の採り方が劇的に変わると期待している。

「漆は木の幹だけではなく、根や葉にも含まれています。新しい技術を使えば、木全体から無駄なく漆を採ることが可能です。さらに、これまで漆の苗を植えてから採れるようになるまで15年程度必要でしたが、新しい方法なら5年から7年くらいの期間で採れると見込んでいます」
もちろん、腕のいい漆掻き職人が採った高級漆はこれからも必要だが、新しい生産方法によって、採れる漆の量が増えれば、漆製品は今より身近なものになっていく。これは漆に関わる人たちが望んでいることだという。
一日も早い衝撃波破砕技術の実用化が望まれるが、それには時間も費用もかかる。松沢さんがみらい基金に応募したのはそのためだ。
「漆の新しい生産方法を確立するところが、今回の取り組みの一番のポイントです。漆の採り方が変わるので、苗木づくりから検討しなくてはなりません。みらい基金の助成金を使って、種を植えるところから採るところまで最善の方法を探り、新しい漆産業を作っていきたいと考えています」
漆の可能性を世界に発信する「漆の里」をつくりたい
浄法寺漆産業が沖縄工業高等専門学校と新しい漆の生産方法を研究していることは、地元岩手の新聞やテレビなどのメディアにも取り上げられている。岩手の宝である漆を見直そうという動きも少しずつ広がっているようだ。
岩手県では今、耕作放棄地が増えている。杉を伐採したあと、再び植栽するのをためらう山主も少なくない。杉は伐採するまでに数十年かかる上、利益が出るとは限らないからだ。その点、漆はより短期間で収益が期待できる。「漆の木を植えたい」という声が、松沢さんに届くことも増えてきた。

「漆への関心が高まっているのは非常に良いことだと思います。私も40代の半ばになり、漆を育てることに関われる期間が限られています。だからこそ、縄文時代から続いてきた漆の文化を、次世代につないでいきたいという想いが、どんどん膨らんでいます」
漆を安定的に量産できるようになるまでは、まだまだ時間がかかるが、ゆくゆくは一関市大東地区を新しい「漆の里」にしたいというのが、松沢さんの願いだ。日本人が古くから親しんできた漆の文化を未来につなげていくとともに、漆そのものが持つ魅力を、「漆の里」から日本全国、世界へと発信していきたいと松沢さんは話す。
「かつてヨーロッパでは、漆はJAPANと呼ばれていました。ヨーロッパの人々にとって、漆は日本を象徴する魅力的な素材だったのです。じっと見ていると引き込まれそうになる艶や、触ったときのしっとりとした質感、手に馴染む感じも漆ならでは。漆の魅力を見て、触れて、感じられる環境をつくりたいです」

漆の魅力に惹かれる企業も増えている。日本を代表する企業とコラボレーションをすることも少なくないという。
「当社のスタッフは少ないですが、日本航空やJR東日本、トヨタ自動車といった大企業と一緒に仕事ができるのは、漆が人を惹きつける素材だからだと思います。漆があるからさまざまな産業の枠組みを越えて、つながることができるのです」
漆の種は蝋に包まれているため非常に発芽しにくい。蝋を硫酸で溶かすなどの手間がいる。発芽した後も、漆の木が小さいうちは刈り払いをしないと、周りの雑草に負けてしまう。つまり、日本人の文化に欠かせない漆の木を大きく成長させるには、人の力が必要なのだ。日本人と漆の不思議な共生関係は、これから生まれる「漆の里」で発展しながら、遠い未来へと続いていくことだろう。






