栗の名産地が抱える生産の課題が、年々深刻化

栽培面積、収穫量ともに14年連続日本一を誇る栗の名産地、茨城県。なかでも笠間市は代表的な栗の産地として知られている。しかしながら、生産農家の高齢化、後継者不足といった問題は、この地域でも深刻化していた。

笠間市の山口市長は、栗生産の課題についてこのように語る。
「農業全般にいえますが、まずは後継者がいないこと。そして市全体の収穫量は多いのですが、一定の作付面積に対する収穫量が全国平均より少ないこと。さらに収穫した栗はすべてが商品化できるわけでなく、品質が悪いものが約2割あるのでこれの活用法。栗をむいた後の殻などの残渣(ざんさ)の問題。これらにどう向き合うかは、笠間市の栗生産にとって大きな課題となっていました」
栗生産の現場にICT技術を導入し、地域課題の解決に挑む

公益財団法人鯉淵学園は、伝統的な価値観にとらわれない広い視野と科学的な考え方のもと、実践重視の教育を行っている。学園長の長谷川さんは、地域貢献という観点から笠間市の栗生産の課題について思いをめぐらせていた。
「笠間市は栗の産地として有名なんですが、栗の生産が強いというわけではないんですね。栗農家の大多数は高齢者で、生産の中で廃棄される栗も非常に多い。自分たちにできることは何かないかと考えていたのです」

長谷川さんらは議論を重ね、あるプロジェクトを発案した。
「学校で実践しているICTの知識や技術を栗の生産現場に活用できないか、検証活動を行うことにしました。さらに生産される栗の規格外品を豚の飼料として再利用して"マロンポーク"というブランド豚をつくるアイデアも生まれました」と、長谷川さん。
こうして、笠間市の栗生産の課題解決に向けた新たな挑戦が動き出した。
栗畑を自動管理するICT技術で、農作業の身体的負担を軽減

栗の生産現場へのICT技術の活用とは、どういうものか? 鯉淵学園 みらい基金プロジェクト担当の小田野さんは、その仕組みを説明する。

「みらい基金の助成金で、畑アシスト機器というセンサーを導入しました。このセンサーは栗の圃場に設置することで、土壌の成分を分析することができます。これまでは栗農家さんの経験値やスキルによって推測されていた土の状態がこのセンサーを使うことで数値化できるので、これから栗農家をやろうという方が始めやすくなるというメリットがあります」

「そして、下草を自動で刈り取るロボットも導入しました。栗の圃場面積は広いため、下草刈りを人の手で行うとかなりの身体的負担になりますが、これを軽減します。また、下草刈りの季節はとても暑い時期が多いので、熱中症などの事故を防ぐことにもつながると思います」とその効果を話す。
廃棄される栗を再利用して、新たなローカルブランドを育てる

廃棄される栗の利用法については、小田野さんはこのように説明する。
「栗農家さんから規格外の栗を回収し、豚の飼料にしてブランド豚を開発する取組みを行っています。豚のエサにするには栗を細かく砕かなければならないので、粉砕機を導入して使用しています」

「また、栗を飼料として与えた場合の豚の成長具合を詳しく調べるため、配合飼料に入れる栗の分量を計測する電子測りと、豚の重さを測定する体重計も導入しました」

栗を配合した飼料で育った豚には、ある特徴的な肉質が見られるという。
「試験を重ねて、栗を与えた豚の肉はちょっと薄いピンク色になることがわかってきました。脂肪の量が若干増えて、いわゆるサシが入ったような肉質になることが認められています」と、その効果に小田野さんは自信を深めている。
ブランド豚を成功させるには、この先の販売や宣伝といったものが重要となってくる。
「行政を含めた多くの関係者とともにプロジェクトを進めていきたいと思います」と、今後の展開にも考えをめぐらせている。
笠間の栗とICT技術の融合が、新たな付加価値をもたらす

鯉淵学園の取組みには自治体も期待を寄せている。笠間市議会 副議長の内桶さんは、笠間市の栗とICT技術を組み合わせた活動についてこのように話す。
「新しい農業の形としてICTを使っていくことは、やはり重要だと思います。笠間の栗と新しい技術でブランド豚が開発できれば、笠間の栗だけではなくICTによって管理された品質のいい豚という付加価値をプラスことができる。そういう意味で意義ある事業だと思いますね」
栗生産の活性化を図り、新たなビジネスモデルを次世代へ

地域貢献という思いから始まった、笠間市の栗生産の課題解決に向けた今回のプロジェクト。その未来について、鯉淵学園の長谷川さんはこのように語る。
「この栗やブランド豚を通して、一次産業だけでなく食の分野にも貢献していきたいという思いがあります。今はイベントなどでテスト販売という形でブランド豚を提供させてもらっていますが、この"マロンポーク"を笠間市のローカルブランドとして確立させて、地域の食として広めていきたいというのがひとつの目標ですね」
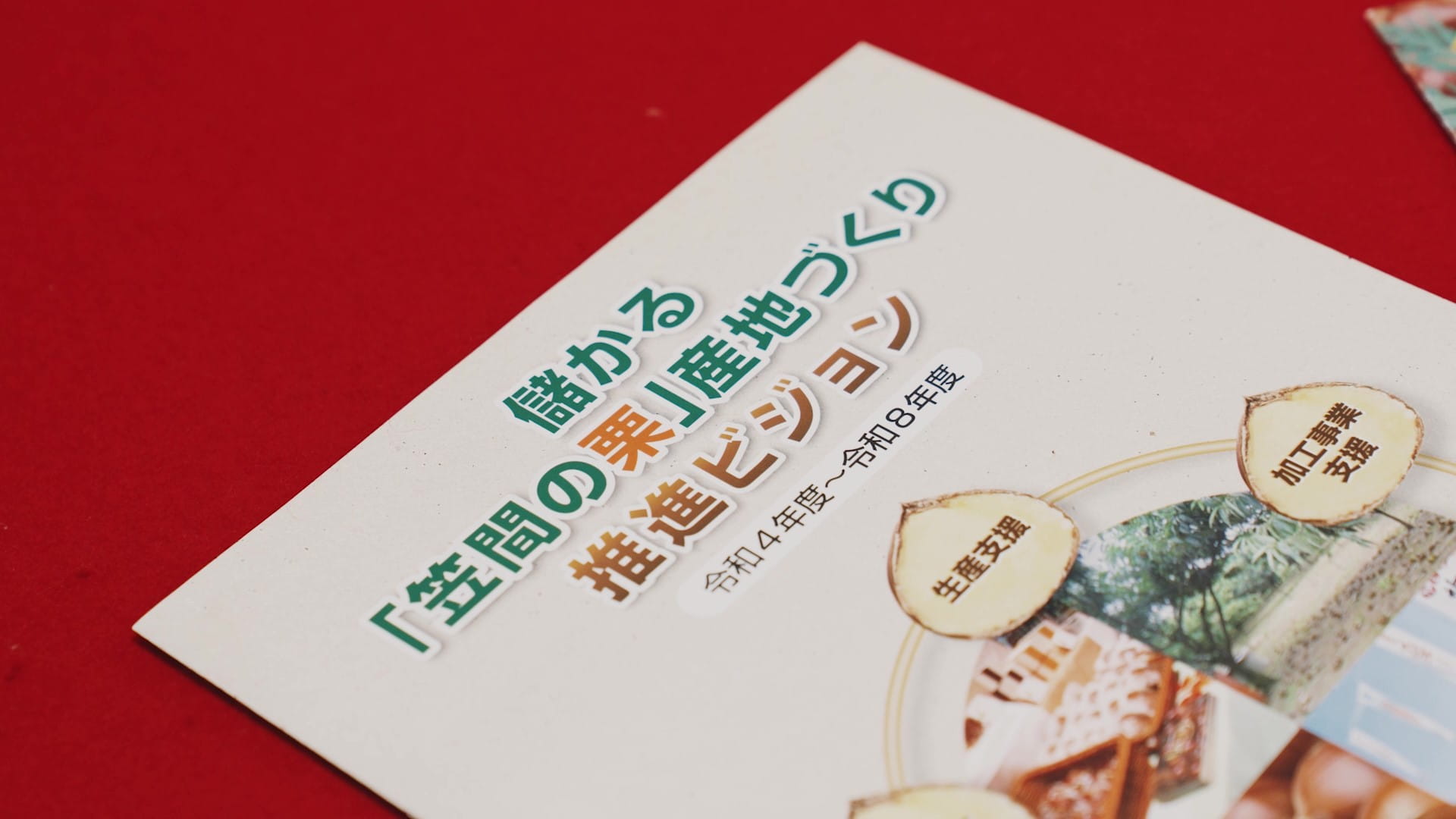
笠間市の山口市長は、このプロジェクトの未来像をこのように思い描いている。
「今回は、地域に根ざした法人組織である鯉淵学園さんに取り組んでいただいているということで、まずはしっかりとした商品として消費者に提供できる形になることを待ち望んでいます。我々としては、笠間の栗をブランド化するのと同様、 "マロンポーク"も生産から加工、販売まで一連の流れをしっかり構築してビジネスとして成立させなければなりません。これが確立すれば、笠間市ならではのビジネスモデルとして新たな取組みに参加していただける農家の方も増えてくると思います。そういうことが、養豚農家や茨城県全体の農業の活性化や収益アップにつながっていくのではないでしょうか」

笠間の栗生産の課題を解決し、新たなローカルブランドを創出していく鯉淵学園の取組み。規格外の栗と最新のICT技術の融合が、地域に新たな活力をもたらしていく。




