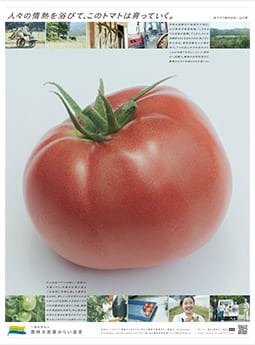深刻な人口減少と高齢化...地域の崩壊まで待ったなし

山陰地方の中山間地域は、平野部と違い広い農地を確保するのが難しい。勾配があるので自動の草刈り機などの農機を使いにくく、重労働も多いという。少子高齢化、過疎化も深刻だ。農業従事者の平均年齢も年々上がっており、特に山口県は全国的に見ても平均年齢が高い。萩市東部の旧田万川町、旧須佐町地域はその典型である。
「この地域には平均年齢が70歳を超える集落営農法人もあるほど、高齢化が進んでいます。ですから、例えば、真夏の草刈りなどの仕事は熱中症の危険も高く、命がけです。後継ぎもいない農家もありますから、このままではいずれ地域が崩壊してしまうのではないかという危機感を抱いています」

そう話すのは、萩市東部の田万川流域にある7つの集落営農法人を束ねる「萩アグリ株式会社」の代表である尾木社長。各集落では、個々の農家が集まって水稲を中心とした営農を行ってきた。その後、徐々に集落営農法人が設立された。2013年7月28日、この地域は大規模な豪雨災害に見舞われたが、集落営農法人が設立されていたことにより、早期の復旧につながった。しかし、災害復旧はひと段落したものの、「それぞれの法人で地域を継ぐものがいない。どうにかしなくちゃいけないという流れの中で、7つの集落営農法人の連合体である萩アグリ株式会社をつくったのです」と尾木社長は話す。
7法人の連携による相乗効果の一つは、スケールメリット。肥料や農薬などを一括で仕入れることによってコストを下げた。また、使用頻度は低いが必要な農機具も、萩アグリで購入し各法人に貸し出す形にした。肥料や農薬、農機具は、廃校になった中学校の体育館を市から借りて保管。一法人ではなく、連合体からの相談ということで体育館の貸し出しの話がスムーズにまとまったという。
みらいの希望が詰め込まれたIoTトマト・プロジェクト
萩アグリは、みらいへの投資も積極的に進めている。この地域は水稲栽培が中心であり、なおかつ積雪もあるため冬場は仕事が少ない。周年雇用がなかなか難しい状況だ。そのためIoTを活用した園芸施設の導入や、露地野菜栽培を行い、地域担い手を確保し、次世代後継者を育成していくこととしている。特に注力するのは、冬春トマトの栽培だ。

山口県萩市は、夏秋トマトのブランド「山口あぶトマト」の産地であり、生産や選果、出荷のノウハウがある。そこで冬春トマトを生産できるようになれば、販売を有利に進められるという考えのもと、2018年8月から冬春トマトの栽培をスタートした。冬春トマトは冬季に暖房が必要で、燃料費などのコストがかかるが、晩秋から初夏にかけて長期間収穫できる。水稲などの収穫が終わった秋から冬にかけても仕事があるので、年間を通じた雇用体制を確立する上で都合がいい作物だ。
萩アグリは現在、耕作放棄地を含む水田を買い取り、そこに一大冬春トマト団地をつくる準備を行っている。みらい基金への申請は、取り組みを加速するための「あと一歩」を求めてのものだ。試験ハウスで冬春トマト栽培のノウハウを蓄積し、当地にあった栽培方法を確立させ、大規模なハウスで量産する計画になっており、助成金はハウスの建設費等に充てられる。

同社の橋本専務は、「イニシャルコストはかかりますが、冬春トマトの栽培は、日照量や温度・湿度、炭酸ガス濃度などをIoTで制御する全自動化を目指してやっていきます。農業経営の合理化を進めて、きちんと収益を上げられる体制を整えることも重要です。少しでも早く足場固めをしたいと考えています」と語る。
試験ハウスで作ったトマトは、道の駅や提携スーパーで既に販売されている。甘さと酸味のバランスが良くとてもおいしいと評判で、店頭に並んですぐに売り切れることもあるという。大量に生産できるようになれば販路を広げられるのはもちろん、直売や加工などで新しい雇用を生み出せる。
地域の力を団結させて「にぎやかな田舎」をつくりたい
萩アグリの連携の輪は、農業以外の団体にも広がっている。萩アグリが核となり、JAやJF、萩市、山口県、自治会、社会福祉法人や道の駅などとともに、「みらいの地域サポート協議会」を発足させ、文字通り地域のみらいに向けた話し合いを始めた。各団体が抱えている課題をヒアリングし、解決に向けて知恵を合わせることによって、地域の活性化・維持発展に向けた具体的な取り組みへとつなげていく構えだ。

みらいの地域サポート協議会のメンバーである田万川ふるさとづくり協議会の会長、港さんは、「元気がなくなりつつある農村で、地域のみらいのための事業を計画されて、前に進まれている萩アグリのメンバーのみなさんには、本当に敬意を表しています。今回の取り組みが、大きなうねりになることを期待しています」と話す。

地域のみらいに向けた取り組みを行政も側面から支援している。萩市田万川総合事務所産業振興部門主任の大石さんは、「7つの法人が連携することで、地域の力は底上げされていると感じています。取り組みに必要な人や情報をつなぐなど、行政ができることを通じて、みなさんの背中を押していきたいです」と話す。民と官が足並みを揃えているところもこの地域の強みだ。
萩アグリのみらいを担う20代前半の若手もいる。それこそ、若手からすれば萩アグリの尾木社長や橋本専務は、祖父母と同じくらいの年齢だが、思い描く地域のみらいは同じである。

試験ハウスでトマトの栽培をしている入社2年目の大田さんは、萩市江崎地区の出身。祖母の手伝いがきっかけで農業に興味を持った。「子どものころから土いじりが好きだし、つくったものをおいしく食べてもらえるところに惹かれて、農業の道に進むと決めました。中学卒業後は、農業高校・農業大学校に進学。萩アグリに就職したのは、 農業を通じて地元を盛り上げるための活動をしているからです。萩アグリのトマトハウスが、地域の活性化の象徴のような施設になればと思っています。そのために自分も頑張っていきたいです」と意気込む。

同じく入社2年目の手嶋さんも、「地域の方はみんなすごく優しいです。自分のことを心配してくれるし、コミュニケーションが活発な明るい地域だと思います。自分に何ができるか分かりませんが、地域をもっと活性化させるお手伝いをしたいです」と話す。
強い連携力を武器に地域づくりを進めている萩アグリの取り組みを見たいということで、他地域から視察団がくることも多い。農業従事者の高齢化や担い手不足は、全国の中山間地域共通の課題。だからこそ、この地域が「にぎやかな田舎」の姿を取り戻すことができれば、日本の中山間地域を勇気づけることにつながるだろう。